この記事は約8分で読めます。

SX(サステナビリティトランスフォーメーション)は、世界的な環境変化やCO2削減意識の高まりに伴い、企業のサステナビリティと社会のサステナビリティの両面から変革を起こすことを意味する概念です。
本記事では、SXを推進するために必要な企業経営の変革と社会的責任、SXへ積極的に取り組んでいる企業を詳しく解説しています。
SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とは?

サステナビリティトランスフォーメーションは、企業のサステナビリティと社会のサステナビリティを同期化し、必要に応じた経営・事業の変革を起こしていくことを意味します。
企業が社会に対して持続可能で長期的な価値提供を行い、社会の持続可能性の向上、持続的・長期的な成長力の向上、更なる価値の創出につなげることを目指すものです。
2019年11月から経済産業省が「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」も設置し、SXへの施策も具体的に発表しています。
SXはなぜ注目される?

SXが注目される背景には、企業の社会的責任と持続性のある成長、人材資本の観点が関係しています。企業の社会的責任と人材資本経営の背景からご紹介します。
企業の社会的責任
世界的にも広がっているSDGsとESGの2点から、経済資本の観点だけでなく、企業にも未来の環境や持続可能な社会の実現を求める意識が高まっています。
SDGsでは単なるリサイクルだけでなく、持続可能な社会を実現するための環境負荷軽減の取り組みについて、具体性を持たせることが求められています。
またESGも環境・社会・ガバナンスの3点を柱として、国連が国際的な投資の判断基準に記載しており、企業にとって軽視できないポイントです。
従来のように利益だけを追求する企業体質では、環境意識や社会的責任を果たすには不十分と評価されるようになりました。
社会の意識の変化に伴って、SXが企業の社会的責任を果たす要因の1つとなり、持続的な成長を続けるための鍵になっています。
人材資本経営
SXの対象は企業の成長に大きく関連する人材の育成、ダイバーシティや多様性にも及びます。
企業が持続可能性を高め、継続的に成長していくには、従業員を育成し、働き方も時代に合わせて変化する必要があります。
国はSDGsやESGの方針の策定、取組への支援を行っていることから、企業は今ある人材資源をいかに有効活用するかが重要です。
SXを企業経営に取り入れることで、人材の育成と有効活用の観点から持続的な成長の可能性が高まると期待されています。
企業として向き合うべき理由

SXの中心となっているCO2削減の課題については欧州が最も規制面でリードしており、現在「Fit for 55」という目標を掲げています。
「Fit for 55」は1990年比CO2削減量を55%以上にするという包括的な政策パッケージとなっており、多くの既存立法に対する目標数値の上方修正などの改正提案や新たな規則などがその中身となっています。
当然ながら企業もそれらの目標に対してのアクションを求められており、メルセデスベンツでは30年には20年比で乗用車1台あたりのライフサイクルCO2排出量を50%削減する目標を打ち出しています。
また、世界最大級の物流会社であるDHLではラストワンマイルのEV化を進め、2030年までに6割をEVで配達することや、取締役のボーナスの30%のウェイトをESG目標の達成率が占める、持続可能技術への投資や燃料に対して2030年までに70億ユーロ以上を投資するといった目標を定めています。
一方で、荷主が上乗せ料金を支払えば二酸化炭素(CO2)排出量を減らせるサービスなどCO2削減を契機とした売上向上にも取り組んでいます。
このように欧州でビジネスを行う場合にはEUのルールに従う必要があるため、企業としても真剣に取り組む必要があります。
また日本を国際比較するとCO2排出の企業負担(日経記事2023年5月6日「CO2排出の企業負担、日本は欧州の7分の1 削減圧力弱く」より)は小さく、今後プレッシャーが高まる可能性があるため、グローバル企業に限らず対応を検討していく必要があると思われます。
注意頂きたいのは、CO2削減を行うコストのかかる活動とだけ捉えると規制対応という位置付けになりますが、自社の戦略や新たな商品・サービスを見直す契機とすることで自社の競争力向上につなげられる可能性がある点です。
DHLの新サービスのように付加価値を高めたり、例えば自動車部品メーカーであればEVは難しくとも、ガソリン対応パーツを見直して水素対応パーツを開発することで今後の成長につなげるような検討ができるため、是非企業として何ができるかを幅広くご検討ください。
本サイトの運営ならびに記事の執筆を行っているムーンプライドでは新規事業の立ち上げや推進に関するコンサルティングサービスを提供しております。
大手企業における新規事業企画、事業の推進支援やパートナー企業との共創事業支援、DX営業支援などを行わせていただいており、ご興味のある方は本サイトの案件登録フォームからお問い合わせください。
また、大手ファーム出身のコンサルタントも募集しておりますので、案件をお探しの方はfirmgradsからご登録をお願いいたします。
SXの取り組み事例
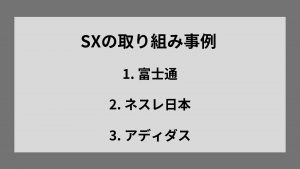
国内・海外ではどのようなSX取り組みがされているのか、3つの事例をご紹介します。
富士通
富士通は2013年以降「FT&SV」を毎年公表しており、2023年はその中に「デジタルイノベーションによるサステナビリティ・トランスフォーメーションの実現」を掲げています。
FT&SVの根底にはヒューマンセントリック、データドリブン、コネクテッドの3つのキーワードがあり、再生型社会実現に向けた具体的なアクションを提言しています。
具体的なSXの取り組みは、以下の5つです。
- 自動化:AIを活用した自動化による人口減少社会での生産性向上
- エクスペリエンス:リアルとデジタルの融合によるインクルーシブな購買体験
- イノベーション:HPCとAIを活用した創薬やゲノム医療による健康増進
- レジリエンス:モビリティ・デジタルツインによる渋滞の緩和とCO2の削減
- 材料と製品のトレーサビリティ改善によるリサイクルと廃棄ロスの削減
そして取り組みの鍵となるテクノロジーメガトレンドも設定し、AI、AR・VR、6Gなど次世代技術を現実世界に取り込むボーダレス・ワールドの構築も目指しています。
加えてユーザーから広く意見を取り入れることで、さらなる発展を目指しています。
ネスレ日本
ネスレ日本は「生活を豊かにする食の持つ力を信じます」を信条に、グローバル企業としてのリソースと専門知識を生かしたSXを推進しています。
CSV(共通価値の創造)ではパーパスとして「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」とし、社会や地球環境に有益な事業構築を目指しています。
そのうえで温室効果ガスの削減量、女性管理職の割合などを公表し、グローバルでの取り組みも公式サイトにて公表している先進的な企業です。
持続可能な方法で栽培・調達した原材料、2030年までの目標設定した再生農法とコーヒーの苗木の植樹、サーキュラーエコノミーの構築なども進めています。
また主力製品のキットカットのカーボンニュートラルに取り組み、2025年までに原材料調達・製品製造・配送などで生じる温室効果ガスを50%以上削減することも公約にしています。
アディダス
海外の事例ではドイツのスポーツ用品メーカーのアディダスが、PEOPLE・PRODUCT・PLANET・PARTNERSHIPの4項目でSXを推進しています。
PEOPLEでは従業員向けの行動規範を改定し、ボランティア活動への従事、工場労働者向けホットラインの拡大などを行いました。
PRODUCTでは使用するコットンをサステナブル・コットンにすることを公約にして、製品の再生ポリエステル繊維の量も増加させています。
PLANETではサプライヤーへの環境監査、省エネルギー化のための設備投資も行いました。
PARTNERSHIPでは世界的な企業の一員として、アディダスは世界標準を取り入れたSXを進めている段階です。
SXに対する取組み方の指針

これまでSXについて取り上げてきました。
CO2が注目されがちなキーワードですが、決してそれだけではなく、環境や社会に対して良いことを行い、持続的なビジネスを行っていくために重要なことが一貫短期的な利益と相関せずともきちんと対応するということだと思います。
古くからの近江商人の経営哲学である「三方よし」とも共通する考え方と捉えるとわかりやすいのではないでしょうか。
若い方は中高年に比べるとソーシャルグッドを重視しているということも言われており、今後の主要顧客となりうる若年層のファンを作りブランドを育てていくという観点でSXに取り組むことで売上向上にも寄与するというような観点があるとSXに対する社内の合意形成も図りやすいと思います。
まとめ
地球温暖化や環境問題が社会の共通課題として認識されるようになり、企業にも環境改善や社会的責任を求める声が高まっています。
SXは大企業だけが取り組むべきものではなく、中小企業やベンチャー企業にとっても取り組むべき課題です。
むしろSXをチャンスと捉え、中小企業の中には積極的な取り組みで知名度を上げ、経営戦略に一部にしているところもあります。
持続可能な社会を実現するためには、企業規模の大小を問わず社会的な責任を果たし、人材資源を有効活用しながら成長を目指すことが重要になるでしょう。
TACHIAGEでは、企業の戦略・企画やデジタル化、業務改革・IT構築、新規事業などのコンサルティングをサポートします。企業としてどうSXに向き合い・取り組むかをお考えの方はTACHIAGEに相談ください。





